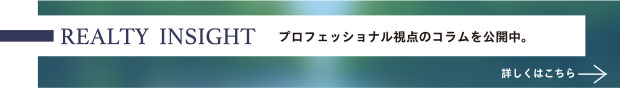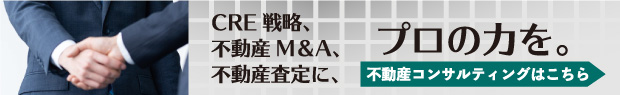日本国内のM&A件数は2020年度3,789件、2021年度4,334件、2022年度4,096件、2023年度4,211件、2024年度4,695件と増加傾向※1にあります。背景にあるのは、主に中小企業の後継者問題や採用難に起因する人手不足であり、企業独自の施策での解消は難しいため、対策としてM&Aが採用されるケースが多いと見られています。
一般的にM&Aは買収対象企業の事業を自社に統合するために行われますが、最近は「不動産M&A」という、企業不動産の取得を目的としたM&Aが注目されています。
「一般的なM&A」の場合、買収対象のなかに不動産を含むことがあっても、買収主体は「事業」です。これに対し「不動産M&A」の主体は「不動産(+付随する事業)」であり、不動産を取得するために対象企業ごとM&Aをするという形になります。
不動産M&Aは、不動産関連企業(不動産管理会社、不動産関係のコンサルティング会社など)が当事者(特に買い手)になるケースが多く、
A)対象の不動産を所有する会社を株式譲渡により子会社化する方式
B)対象の不動産のみを新設会社に分割移転と株式譲渡を組み合わせ、子会社化する方式
の2つのタイプが一般的です。
A)のケースでは対象企業の全株式を買い手企業が取得し、その企業を完全な子会社とすることにより目的の不動産を間接的に所有することになります。買収した企業の事業の採算性・将来性が低く、事業整理以外を選択しづらいケースなどで行われ、所有した不動産を運用することで収益性を高めてから、売却することで利益を得るという形です。
B)のケースでは会社分割(新設分割)と株式譲渡を組み合わせることにより、不動産を中心とする事業のみを切り出して買い手企業が取得します。新設分割のプロセスとしては、売り手企業が不動産を所有する事業を新会社として設立することにより、買い手企業は新会社ごと不動産を取得することになります。
不動産M&Aで会社の売買という形をとる理由としては、不動産の単純な売買よりも課税面のメリットが大きいことが指摘されています。もちろん、税制上困難なケースはありますが、例えばBの不動産M&A方式(新設分割+株式譲渡)スキームでは、承継される資産・負債の譲渡損益に対する法人税、対価が株主に交付される場合の配当所得に対する所得税、不動産の承継に対する不動産取得税が、組織再編税制の適格要件などを満たすことで非課税となることも期待できます。
こうした不動産M&Aのメリット・デメリットについてはケースによって変わるため、様々な検証を行ったうえでの手段の採択が必要となります。
主な不動産M&Aの事例としては、※2
不動産会社同士のM&A事例
事例1)買い手:株式会社AVANTIA、売り手:ドリームホームグループ
2021年4月、注文住宅事業、戸建分譲事業、リフォーム事業を展開するAVANTIAが、京都で戸建住宅事業を展開するドリームホームグループを子会社化。
東海エリア中心に戸建事業を展開していたAVANTIAは、京都府内No.1の戸建供給実績を誇るホームグループを傘下に入れることで、関西での事業展開を推進。
事例2)買い手:トーセイ株式会社、売り手:株式会社アイ・カンパニー並びに系列4社
不動産の開発や賃貸事業、コンサルティング事業等を展開する東証プライム上場企業、トーセイは、優良な不動産を取得し、収益性を高め売却するといった事業モデルとして、2001年から2018年までに13件の不動産M&Aを実行。
2021年9月、都心で区分マンションの買取再販を展開しているアイ・カンパニー並びに系列4社の子会社化により、事業領域の拡大に成功。
異業種によるM&A事例
事例3)買い手:株式会社DYM、売り手:株式会社エイジアトラスト
2021年3月、Web事業や人材事業、海外医療事業他を展開しているDYMが、不動産コンサルティング事業を展開するエイジアトラストを子会社化。
法人向けのオフィス移転に関するコンサルティング事業を展開するエイジアトラストを傘下に収めることで、DYMはオフィス移転や店舗開拓のニーズを獲得。
事例4)買い手:京王電鉄株式会社、売り手:株式会社サンウッド
2021年11月、富裕層を対象とした新築マンションの分譲事業が得意なサンウッドの株式を京王電鉄が取得し、資本業務提携を実施。
京王電鉄は、本提携により鉄道事業の他に展開している分譲マンション事業部門を強化。
「不動産M&A」は、一般的なM&Aと比較しても取得する不動産アセットの先見性といった知見が必要となり、高い専門性を要求される事業戦略といえます。